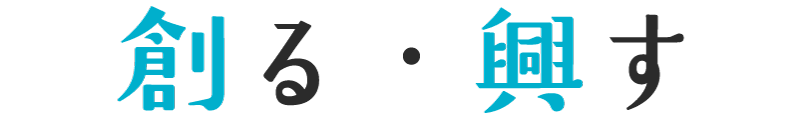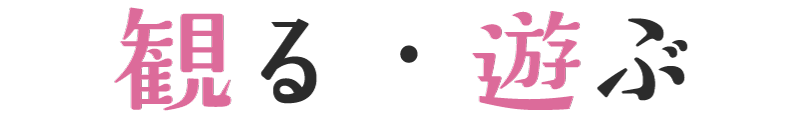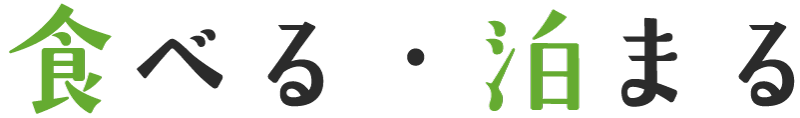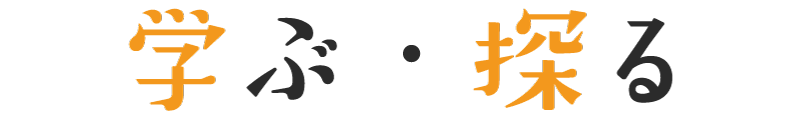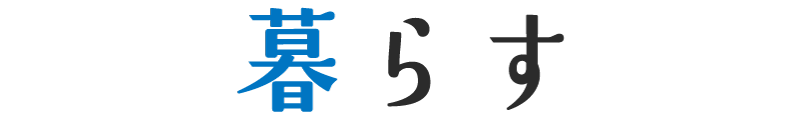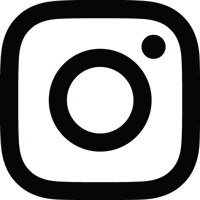若松のポテンシャルで北九州を興す
北九州市議会議員三原あさとさん
若松を興す

北九州市議会議員 三原あさとさん
趣味・特技は剣道という三原あさとさんは五段の腕前。「途中、一度剣道から離れましたが、苦しい時期に救ってくれたのも剣道だった」とのこと。そんな三原さんが政治家を志したきっかけは12年前の福岡市長選挙だったそうです。選挙後、市長の決断が「まち」を動かすことを実感し、その4年後、37歳の時に北九州市長選挙に立候補しました。結果は惨敗だったものの、2017年の市議選では当選を果たして現在2期目。北九州市の再生を掲げる三原さんにその思いをうかがいました。
三原さんにとって若松の魅力は何ですか?
三原さん:小・中・高、そして現在も高須に住んでいますが、現役を退いたシニアの方々が地域のために頑張っておられますし、北九州市のなかでも若松のポテンシャルに注目する意見を度々耳にします。
若松の魅力は、南海岸通りのレトロな町並みと学研都市の新しい街並みが融和した住環境ですね。学研都市はこの10年間で人口が約3倍になりました。かつて新興住宅地であった高須や青葉台も人口が減少しているとは言え、退職されたシニアの方々がまちづくりに励んでいます。二島や鴨生田などもアクセスの良さから、戸建ての空き家探しが難しいほどの人気だそうです。
自然に恵まれ、農業や漁業も盛んで、響灘地域には新たな工業団地が形成されています。親と同居できないが、近くに住んで面倒を見たいという人たちが学研都市周辺に住み、大学や研究機関など教育環境が整いつつある状況が学研都市の魅力を高めています。

若松のポテンシャルとは何ですか?
三原さん:やはり、2001年に開設された学術研究都市ですね。半導体産業を基軸にした都市形成を目標に大学の研究機関や関連企業が集積し、生活環境も整い、居住人口が増加しています。
また、九州大学の伊都キャンパスに近い糸島や、台湾の半導体メーカー(TSMC)が進出した熊本などに比べても、遜色のない立地条件が整っています。物流拠点として北九州空港の可能性も高まっていますから、学研都市のポテンシャルはもっと高まると思います。
ポテンシャルを活かすには何が必要ですか?
三原さん:未来に向けての思い切った投資とスピード感だと思います。世界で6番目の規模を誇る台湾の半導体メーカー(PSMC)の誘致合戦は、結局、宮城県に軍配が上がりました。直ぐにでも大規模工場を建設したいとの要望に応えられなかったのが敗因だと思います。
若松北海岸地域の観光化を進める上でもネックになっていますが、企業誘致を促進する上で市街化調整区域を見直すことが、都市のブランディングという観点からも必要です。

北九州の「モノづくり」にも課題が多いと思いますが・・
三原さん:そうですね。特に製造業に従事する企業の雇用環境が厳しいようです。中小企業の中には独自の技術を保有し、個性的で魅力ある会社も多いですから、そうした会社の人手不足を解消する取り組みが第一でしょうね。
若松の有志企業と区役所が企画した地元高校生の企業見学ツアーでは、実際に働く現場を訪れたことで関心が高まったようです。参加した学生たちの反応は、「できれば家族や友人のいる地元で働きたい」という声が大半だったと聞いています。こうした地元企業と学生たちが互いに情報共有できる環境を整えることも、雇用問題解決の一助になるのではと思います。
少子高齢化・人口減少が指摘されるなか、若松ではどんな対策が有効ですか?
三原さん:若松に限らず北九州市全体に言えることですが、やはり魅力ある雇用環境の拡大だと思います。関連産業の立地や学術振興が期待できる半導体など、先端産業の誘致を実現することが肝心です。
次に重要なのは交通インフラの整備です。北九州空港を含め小倉都心と市内主要拠点を乗り継ぐことなく巡回できる環状路線があれば、人流の活性化につながります。学研都市や高須地域と小倉都心が直結すれば、学研都市のポテンシャルが一層高まると思います。
また、響灘工業団地で働く人たちの若松居住を促進する方策も必要ですし、南海岸エリアの人流を拡げるため、若松駅周辺に渡船乗り場やバスターミナルを集積させるのも有効なアイデアです。

高齢社会に向けた対策という観点からですと、市営バスの運行をAI分析したり、予約システム化を進めるなど、利用者の実態に即した方法を検討することが必要だと思います。特定エリアとして学研都市周辺を実証実験の場にすれば、北九州市のイメージ発信にも繋がると思います。
「少子高齢化」をネガティブに捉えるのでなく、新たなビジネスを発想する好機とみなすことから、都市再生のアイデアが生まれるのではないでしょうか。
三原あさと市議会議員の施策等、詳細は、https://miharaasato.jp/policy/をご覧ください。